映画館で『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』を見終えた後、「なんやこれ…?」「え、どういうこと…?」って、頭ん中が「?」でいっぱいになりました。前作のジョーカーが大好きだったので、期待していたものと全然違って超がっかり。そんな人も多いんやないでしょうか。
ネット見ても「最高傑作や!」「いや、意味不明な駄作やろ!」って、見事に評価が真っ二つ、というわけでもなく、低評価が圧倒的。前作が好きやった人ほど「思てたんとちゃう!」ってなったかもしれへん。
そんなモヤモヤを抱えていたら、U-NEXTの見放題に『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が出てきたいたので、家でがっつり見返しました。そしたら…「ワイ、この映画好き!」ってなったで!笑
なんでこんなに賛否両論なんか?あのミュージカルは何やったんか?最後のシーン、アーサーは結局どうなったんか?
そのモヤモヤ、全部スッキリさせたるで!
この記事は、こんな構成になってます。
- 【前半】サクッと知りたい人向け!簡易版解説
- 忙しい人でも大丈夫!映画のポイントを分かりやすーくまとめたで!
- 【後半】ガッツリ知りたい人向け!ネタバレ完全詳細版
- 時間のある人はこっち!物語の隅々まで、徹底的に掘り下げて解説するで!
ほな、行くで!
【前半】サクッと知りたい人向け!簡易版解説
まずは手っ取り早く、この映画の「なんで?」に答えていくで!
結局、どんな話やったん?
一言で言うとな、これは「ジョーカーをやめる男の話」やねん。
前作で悪のカリスマになったアーサーやけど、今作では社会が作った「ジョーカー」っていう偶像(アイドルみたいなもん)を演じることに疲れ果ててしもうたんや。彼の願いはただひとつ――「ジョーカーではなく、アーサーという一人の人間として見てほしい」。
でも、皮肉なことに、彼の周りの人間…恋人のリーも、彼を崇拝するファンも、誰も「ただのアーサー」なんて求めてへんかった。みんなが求めてたんは、刺激的で暴力的な「ジョーカー」だけ。この絶望的なすれ違いが、この映画の悲劇の核心や。
つまり今作は、偶像に囚われた男の悲劇なんや。
たとえていうと、現代のSNS環境でなんとなくバズってたまたまインフルエンサーっぽい地位になってしまった一般人が、SNS疲れを起こして「普通の自分を愛して!」となったんだけれど、「誰も普通のあなたなんかに興味ないですよ、数字がなくなったあなたなんて存在価値ないじゃん!」っていう現実を突きつけられる感じですな。
なんで急にミュージカルになったん?
「いきなり歌い出してビックリしたわ!」って人、多いやろな。
あれな、ほとんどがアーサーの「妄想」やねん。(ここは前作と同じやな。現実か妄想か、どっちの解釈でもええように作られてるんやな)
現実のアーサーは、誰にも相手にされへん、口下手で「サムい」男。そんな彼が、唯一、現実から逃げて、愛する人と心を通わせたり、スターになって拍手喝采を浴びたりできる場所が、頭の中のミュージカルステージやったんや。
つまり、現実がツラすぎて、華やかな歌と踊りの世界に逃げ込んでたってこと。そう考えると、あのキラキラしたシーンが、逆にめちゃくちゃ切なく見えてこーへんか?
現実では孤独で惨めな彼が、頭の中だけでは華やかな舞台のスターになれる。歌と踊りは、現実の痛みからの逃避であり、自己表現の手段だったんやな。
ほな、なんでこんなに評価が分かれるん?
理由は大きく分けて3つあるわ。
- 「思てたんとちゃう!」問題
前作のファンは、もっとジョーカーが社会に反逆して大暴れする話を期待してた。せやのに、出てきたんは「ジョーカーやめたい…」ってウジウジ悩む、弱くて惨めなアーサー。この期待とのギャップが、低評価につながったんやろな。 - 「救いがなさすぎる」問題
この映画、エンタメっていうより、観てるこっちの心をえぐってくる「社会派映画」やねん。特に、自分も社会でしんどい思いをしてる人からしたら、アーサーが最後まで誰にも理解されず、救われへん姿を見るのは、自分のことのようにツラい。カタルシスどころか、絶望感だけが残る。そら「こんなん見たくなかった」ってなる人もおるわな。 - 「エンタメ性より自己批評」問題
アクションや暴動の派手さより、「ジョーカーという偶像とは何か?」というメタ的なテーマに振り切った。映画的挑戦やけど、エンタメを期待した人には不親切に映ったんやな。
ラスト、アーサーは死んだん?
若い囚人に刺されて死んだように見えたけど、実はあれも「妄想」かもしれへんのや。
作中に何回か「アニメ」が映るんやけど、「アニメの後は妄想シーン」っていう法則があるって考察があってな。最後の刺殺シーンの直前にもアニメが映るから、あれもアーサーの頭の中の出来事かもしれへん。(妄想であるならば、つまり、アーサーはもう疲れ果てて死にたかったんかもしれんな。誰も自分を理解してくれない現実に疲れたんや。)
監督がワザとどっちとも取れるように作ってるから、正解はない。「答えは、あなた次第です…」ってやつやな。
ただ、どっちの解釈でも「アーサーが生み出した狂気が、ブーメランみたいに自分に返ってきて滅ぼされる」っていう、皮肉で救いのない結末には変わりないわ。
そして若い囚人という、「新たなジョーカーの誕生」とも取れる。ぼやけて見づらいけれど、アーサーを刺殺した後に、若い囚人は自分の顔を刺してるんや。はっきりとは見えないけれど、たぶんジョーカーのような口になるように口を切ってるんやと思う。続編を期待させるような終わり方やね。
で、この映画が一番言いたかったことは?
ズバリ、「作られたイメージ(虚像)に振り回されたらアカンで」ってことや。
そして、ワイら観客に向けて「お前ら観客もまた、ジョーカーという虚像を消費してるんちゃうか?」っていう、強烈な問いかけでもあるんや。
…と、ここまでが簡易版や!
なんとなく、この映画のややこしさが分かってきたやろか?
「もっと詳しく知りたい!」「なんでそう言えるんか、根拠も教えてくれ!」
そんな知的好奇心旺盛なあなたは、ぜひこのまま後半の詳細版に進んでくれ!ここからが本番やで!
【後半】ガッツリ知りたい人向け!ネタバレ完全詳細版
ようこそ、ディープな世界へ。
ここからは、ネットの情報とワイの考察をフル動員して、この映画の骨の髄までしゃぶり尽くすで!
1. はじめに:これは「ジョーカーという物語」への鎮魂歌(レクイエム)や
前作『ジョーカー』がただの映画で終わらんかったのは、みんな知ってる通りや。あれは一つの「社会現象」になった。社会から疎外された人々の怒りや悲しみの象徴として、アーサー・フレックという男は「悪のカリスマ」に祭り上げられた。
で、今作『フォリ・ア・ドゥ』は、その社会現象そのものに対する、作り手からのアンサーであり、痛烈な自己批評でもあるんや。
「あんたらが熱狂したジョーカーの中身は、こんなにも弱くて、惨めで、ただ愛されたかっただけの男やったんやで」と。前作でジョーカーを神格化したワイら観客に、冷や水を浴びせ、現実を突きつけてくる。
これは単なる続編やない。前作が生み出してしまった「偶像」を、作り手自らの手で解体し、弔うための物語なんや。
(それとこの映画が前作ほど過激になれなかった理由もあるで。なんでかっていうと、まさに前作のジョーカーがあまりにも凄すぎて社会現象になってしまったからや。つまり「映画の影響が社会に与えすぎて困る」問題があって、実際にそれでいくつかの犯罪もあったやん?だから監督らは「社会現象にはならないように」という縛りプレイで映画を作るしかなかったんやな。)
2. 物語の全貌:あらすじを徹底的に追うで!
映画の流れを、もっと詳しく見ていこうや。
- 【起】アーカムでの出会いと「俺と俺の影」
物語は、前作から2年後のアーカム州立病院から始まる。冒頭に流れる短編アニメ「俺と俺の影」。ここで描かれる「影」は、アーサー本人とは別に、勝手に暴れまわる「ジョーカー」という偶像のメタファーや。この映画が、アーサー本人と「ジョーカー」という影の乖離を描く物語であることを、最初から示唆しとるんやな。アーサーは「ジョーカーは別人格」という弁護戦略のもと、裁判を待つ日々。そんな中、音楽療法で歌うリー(ハーレイ・クイン)と出会い、一瞬で心を奪われる。彼女は「あなたの大ファン」と言い、二人は急速に惹かれ合う。この出会いも、後述する「妄想」の可能性が高いんやけどな。 - 【承】妄想の恋と現実の裁判
アーサーとリーの関係は、妄想のミュージカルシーンで華やかに描かれる。彼らはステージの上でデュエットし、完璧な恋人同士になる。でも、現実の裁判は厳しい。地方検事補ハービー・デント(後のトゥーフェイスやな)は、アーサーの心神喪失を認めへん。さらに、アーサーの弁護士から「リーはあんたに嘘ついてるで。彼女は精神病患者やなくて、精神科医や」と衝撃の事実を知らされる。ここで、アーサーが信じていた「唯一の理解者」という存在が、ガラガラと崩れ始めるんや。 - 【転】「ジョーカーはいない」という魂の叫び
リーに裏切られ、追い詰められたアーサーは、法廷でとんでもない行動に出る。ジョーカーのメイクを施し、虚勢を張ってパフォーマンスをする。せやけど、ゲイリーら元同僚の証言に心を揺さぶられ、ついに彼は叫ぶんや。「ジョーカーはいない。6人を殺したのは、この僕、アーサー・フレックだ」これは、社会が、リーが、信奉者たちが押し付けてきた「ジョーカー」という役割(虚像)を、自らの手で脱ぎ捨てた瞬間やった。彼はただの弱い人間に戻りたかったんや。
しかし、その叫びは誰にも届かへん。信奉者たちはブーイングし、リーは失望して席を立つ。彼らは「弱いアーサー」なんて見たくなかったんやな。 - 【結】偶像の終焉と、終わらない狂気の連鎖
アーサーの告白の後、裁判所の外で爆弾テロが起きる。信奉者たちはアーサーを「解放」するけど、彼はもうその気はない。逃げ出したアーサーが向かったのは、思い出の階段。そこにリーがいた。しかし、彼女は「ジョーカーじゃないあなたに興味はない」と冷たく突き放す。すべての希望を失ったアーサーは、再びアーカムへ。そして、若い囚人に「バーに憧れてたピエロのジョーク」を聞かされながら、「報いを受けろ」と腹を何度も刺されて死ぬ。
最期にアーサーが見たのは、リーとステージに立つ幻。そして、アーサーを刺した囚人は、恍惚の表情で自らの口を切り裂き、新たな「ジョーカー」の誕生を暗示して、物語は幕を閉じる。
3. 主要人物の深層心理:彼らは何を考えていたんか?
キャラクターの内面をもっと深く掘り下げてみよう。
- アーサー・フレック:「人間」になりたかった男
彼の根源的願望は、終始一貫して「ただの人間として承認され、愛されること」やった。コメディアンを目指したのも、病的な笑いを「人々を幸せにする笑い」に変えることで、自分の存在を肯定したかったから。せやけど、社会は彼を人間として扱わんかった。
しかし前作でアーサーは、「ジョーカー」という仮面を被ることで初めて他者から注目された。
笑いものにされるだけの孤独な男が、仮面を被った途端に「革命の象徴」になったんや。
そらアーサー自身も「これが本当の自分なんやろか?」って錯覚してまうわな。彼は「ジョーカー」という役割を演じることでしか、承認を得られへんかったんや。
けど今作ではその反動がきっちり描かれる。「ジョーカー」として見られることが増えれば増えるほど、本当のアーサーは透明になっていく。本作の彼は、その役割に疲れ果て、最後にはそれを投げ出す。これは「弱者男性が、社会が求める“強者”の仮面を被ろうとして失敗し、絶望する物語」とも読める。だからこそ、同じように社会で「強者になれなかった」と感じる一部の観客には、彼の惨めな姿が自分事のように突き刺さり、強い不快感や拒絶反応を引き起こしたんやろうな。
これって単なるキャラ設定の話やなくて、ワイらの現実でも起きることやと思うんや。
「職場での役割」「SNSでのキャラ」「家族の前での自分」……そういう仮面に縛られて、素の自分を見てもらえへん苦しさ。
ジョーカーは極端な形で、それを突きつけてくるんやな。 - リー/ハーレイ・クイン:物語を消費する「観客」の化身
次にガガ様演じるリーや。
彼女、最初は「アーサーを理解してくれる唯一の人」に見える。
でも物語が進むにつれ、「あれ、ほんまに理解しとるんか?」って怪しくなっていく。彼女は、アーサー・フレックという人間を愛したんやない。彼女が愛したのは、「ジョーカー」という刺激的で暴力的な物語(フィクション)そのものやった。彼女は、アーサーという素材を使って、自分好みの「ジョーカー」をプロデュースしようとした、とも言える。だから、アーサーがその物語の主役を降りた瞬間、彼女にとって彼は用済みになった。リーのこの姿は、恐ろしいことに、エンタメとして過激な事件や人物を消費する、ワイら観客自身の鏡でもあるんや。ワイらはアーサーの苦悩に寄り添ってるつもりで、実は彼の不幸を「面白い物語」として楽しんでるだけやないか?つまり「ワイらもまた、アーサー本人やなく“ジョーカー”を消費してるだけちゃうんか?」って突きつけてくる存在。 リーは、そんな痛いところを突いてくるキャラクターなんや。ほんでそのメタ的な構造に気づいた瞬間、観客のワイ自身もちょっと胸が痛むんよな。 - ゴッサムの市民(ジョーカー信奉者=ワイら観客):無責任な熱狂の象徴
彼らも同じや。アーサーを救世主や英雄として崇めてるように見えるけど、実際は自分たちの社会への不満をぶつけるための、都合のいい「神輿」として担いでるだけ。アーサーが「ジョーカーやめる」って言ったら、手のひらを返してブーイングする。彼らが求めていたのも、アーサー本人やなくて、「ジョーカー」という便利なアイコンだけやったんや。
彼が病院で刺されたときですら、「ジョーカー殉教」の象徴として祭り上げるだけ。アーサーが実際にどう感じてるか、どんなに苦しんでるかなんて、誰も気にしてへん。
これってめっちゃ怖くない?
現代のSNS文化に似てるんよな。例えば有名人が「本当の自分は違う」と訴えても、フォロワーは「いやそのキャラのままでいて!」って求め続ける。
そして本人が潰れても、「伝説になった」って美化して消費してしまう。まさに偶像消費の地獄や。
だから群衆って、作中のキャラやなく、ワイら観客そのものなんやと思う。この映画の一番胸糞悪いところは、アーサーを消費してる群衆を笑えへんってとこや。だってワイらも映画館で同じことやっとるからな。 - ゲイリー・パドルズ:唯一アーサー自身を見てくれた友達
ゲイリーは身体に障害を持つ小柄な男やけど、基本的にアーサーに優しい。前作でもそうやったけど、彼はアーサーを利用したり笑いものにしたりせず、ただ「一人の人間」として接してる。つまりゲイリーはアーサーが本来望んでた「普通の人間関係」を象徴するキャラなんや。
群衆はアーサーを“偶像”としてしか見いひん。一方でゲイリーは「アーサー=アーサー」として接する。この対比があるからこそ、アーサーが「ほんまは人として愛されたいんや!」って叫ぶ気持ちがより鮮明になる。
彼の法廷での証言は、アーサーにとって「自分が傷つけた無実の人の声」として機能し、これがアーサーの罪悪感を呼び覚まし、「ジョーカー」という仮面を脱ぎ捨てるきっかけとなった。
アーサーはジョーカーではなく自分自身を見てほしかった。けれどアーサー自身も「ただの人殺し」ということが、ジョーカーではなくアーサーを見てくれる唯一の友達から言われてしまったわけやな。
アーサーが「ジョーカーはいない。6人を殺したのは、この僕、アーサー・フレックだ」と告白するのは、まさにゲイリーの証言に心を揺さぶられた直後や。ゲイリーの存在がなければ、アーサーはジョーカーの役を演じ続けていたかもしれん。
4. 映画を読み解く鍵:監督の仕掛けを見破るで!
この映画、いろんな仕掛けが隠されてる。それを知ると、もっと面白くなるで!
- 「フォリ・ア・ドゥ(二人狂い)」の本当の意味
Folie à deux(フォリアドゥ)は医学用語で精神障害の妄想性障害の1つや。この精神障害の特徴としては、一人の妄想がもう一人に感染し、複数人で同じ妄想を共有するってのがある。本作で言うと、単に「アーサーとリーの二人」を指すだけやない。実は、いろんな「二人」の関係が描かれとる。- アーサー ⇔ リー(妄想の共有)
- アーサー ⇔ 社会(狂気の伝播)
- 偶像としてのジョーカー ⇔ 実像としてのアーサー(アイデンティティの分裂)
- メディア ⇔ 大衆(扇動と熱狂)
これらの「二人」の関係性が、互いに影響し合い、狂気を増幅させていく。これこそが「フォリ・ア・ドゥ」の全体像なんや。
- ミュージカル演出の真意:暗鬱ミュージカルの系譜
映画を観終わって一番ザワついたのはここやろな。
「え、ジョーカーが突然歌い出す?」「なんで踊っとるん?」って。
正直、ワイも最初は「これ大丈夫か…?」って思ったで。
でも冷静に考えると、このミュージカル表現はアーサーの内面を映すめっちゃ大事な装置や。
要するに 「現実に耐えられへん男が、自分の頭の中でだけ輝こうとする」 姿なんやな。それがアーサーにできる唯一の表現方法やった。
これ精神医学で言うと、いわゆる「逃避」や「妄想的防衛機制」。
現実のアーサーは孤独で惨めやけど、彼の心の中では豪華な舞台に立ってスポットライトを浴びとる。その落差がむしろ彼の痛々しさを際立たせてるわけや。
この手法は、実は映画の歴史の中にちゃんと系譜がある。『シカゴ』みたいに犯罪と名声をテーマにした法廷ミュージカルや、『ダンサー・イン・ザ・ダーク』みたいに主人公の辛い現実からの逃避として妄想ミュージカル。『ブラック・スワン』は主人公が妄想と現実の区別を失っていく心理ホラーで、これと同じように、アーサーのミュージカル場面も「どこまで現実で、どこから妄想か」がわからなくなる。近年でいうと『ラ・ラ・ランド』は現実には叶わん恋を、音楽とダンスの中で夢みる物語で、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の歌と踊りも 「叶わない願望」 の象徴や。本作は、そういった「暗鬱ミュージカル」の流れを汲んだ、極めて実験的な作品なんや。
しかも、ホアキンとガガは生歌・生演奏で撮影に挑んだらしい。これは、アーサーの妄想に「生々しいリアリティ」を与えるための、監督のこだわりやったんやろな。 - 「アニメーション」が示す現実と妄失の境界線
これが一番のミステリーや。作中、少なくとも4回は印象的にアニメが使われる。- 冒頭: 「俺と俺の影」
- 出会いの直後: アーサーが患者たちとテレビのアニメを見てる。
- 裁判所の爆破直前: 画面の端のテレビにアニメが映ってる。
- ラストシーン直前: アーカムに戻ったアーサーが、うつろにテレビのアニメを見つめてる。
ある考察では**「アニメが映った直後のシーンは妄想」**とされてる。もしこの説が正しいなら、リーとの出会いも、裁判所の爆破も、そして最後の刺殺シーンさえも、全部アーサーの頭の中の出来事やった可能性があるんや。恐ろしい仕掛けやで、ほんま。
5. 衝撃のラストを徹底考察:アーサーはどこへ消えたんや?
あの衝撃のラストシーン、ワイはこう解釈してる。複数の可能性を提示するから、自分にしっくりくるものを見つけてみてくれ。
- 解釈①:現実の死と、偶像の敗北
一番ストレートな解釈やな。「ジョーカー」であることをやめ、「ただのアーサー」に戻った彼は、もはや信奉者にとってカリスマやない。価値を失った偶像は、新たな狂信者によってあっさり殺される。これは、「ジョーカー」という虚像を演じきれなかった男の、惨めな末路や。 - 解釈②:メタファーとしての死と、概念の継承
肉体は死んだけど、それは「アーサー・フレック」という弱い人格の死を意味してるだけかもしれん。彼を刺した囚人が自らの口を裂いたのは、アーサーの中にあった「ジョーカー」という狂気の概念(ウイルスみたいなもん)が、別の宿主に乗り移ったことを示唆しとるんや。ジョーカーは死なへん。誰かに乗り移り、永遠にゴッサムを彷徨い続けるんや。これぞ「フォリ・ア・ドゥ(狂気の伝播)」の究極形やな。 - 解釈③:全部妄想やった説
さっきのアニメの法則を当てはめると、アーサーは今もアーカムの独房で、うつろにテレビを見つめてるだけかもしれん。リーとの恋も、裁判も、死さえも、全部彼の頭の中の壮大なミュージカルやった、という解釈。これが一番救いがないかもしれへんな…。
監督は「観客に解釈を委ねる」って言うてる。せやから、正解はない。ただ、どの解釈にも共通してるんは、前作でアーサーが社会に放った「ジョーク(狂気)」が、巡り巡って彼自身に「報い」として返ってきたっていう、あまりにも皮肉な因果応報の物語ってことや。
アーサーが死んだかどうかは重要やない。大事なんは、「偶像(ジョーカー)が彼を食い尽くす構造」が描かれたことや。たとえ生き残ってても、アーサーはもうアーサーとして存在できん。彼は永遠に「ジョーカー」として消費され続ける。そういう意味で、彼はすでに「死んでる」とも言えるんやな。
最後の群衆の熱狂がまた胸糞悪いんよ。
「ジョーカー死す!」「ジョーカー永遠なり!」って祭り上げてるけど、その裏で「アーサー・フレック」というただの孤独な男が消えていく。
ここ、観客として笑えへんよな。だってワイらも「ジョーカー」というキャラを求めて映画館に来てるからや。その構造に気づいたとき、「あ、これワイら自身の話やん…」ってゾワッとする。
6. この映画が社会に突きつける痛烈なメッセージ
この映画は、観て楽しむだけのエンタメやない。ワイらの社会に対する、強烈な批評であり、警告なんや。
- 暴力の偶像化とファン文化への批判
劇中でジョーカーを崇拝する群衆は、そのまま現実で過激な思想や暴力的な人物をヒーロー視する人々への批判になっとる。「ジョーカー最高!」って熱狂してる劇中のファンは、前作を観て熱狂したワイら観客自身の姿でもある。「お前らも、この無責任な群衆と一緒やで」と、監督は言いたいんかもしれへん。 - メディアと群衆心理の怖さ
アーサーの裁判は、メディアによって完全に「見世物(ショー)」にされる。大衆は真実なんてどうでもええ。ただ刺激的なエンタメとして、彼の不幸を消費するだけ。これは、現実のワイドショーやネットニュースの構造と全く同じや。 - SNS文化とのリンク
この映画で描かれた「偶像消費」って、今のSNSそのままやと思う。- インフルエンサーがキャラを演じ続けて消耗する
- フォロワーは「そのままでいて!」って求め続ける
- 本人が潰れても「伝説になった」って美化して消費する
これって、まんまアーサー=ジョーカーの構造やん。現代社会全体が「アーサーを殺す群衆」になっとるんや。
- 社会システムの不備と弱者排除
アーサーは、精神医療からも、司法からも、福祉からも、完全に見捨てられる。社会のセーフティネットからこぼれ落ちた人間が、どうやって狂気に堕ちていくか。前作から続く、この映画の根源的なテーマや。 - 虚構と実像の断絶
結局、誰も「本当のアーサー」を見ようとはせんかった。みんなが見ていたのは、自分たちの欲望を投影した「ジョーカー」という虚構だけ。これは、ワイらが普段、他人に対してやってることやないか? 相手を深く理解する努力をせず、分かりやすいレッテルを貼って、分かった気になってへんか? この映画は、そんなワイらの「解像度の低い視線」の暴力性を告発しとるんや。
7. まとめ:ほな、ワイらはこの映画から何を学ぶべきか?
この救いのない物語から、ワイらが学ぶべきことは何やろうか。ワイは、アーサーの悲劇を反面教師にすることやと思うてる。
- 外部の虚像に、自分を明け渡したらアカン
アーサーは「ジョーカー」という他人が作ったイメージに自分を乗っ取られて、破滅した。ワイらも、「社会が求める理想像」とか「流行りのロールモデル」とか、そういう虚像に自分を合わせようとして苦しむことがある。でも、大事なのは、自分自身の価値を、自分の中に見つけることや。 - 自分の「弱さ」を受け入れることから始めよう
アーサーの悲劇は、自分の弱さを隠そうと虚勢を張ったことから始まった。弱さを認めるんは、恥ずかしいことやない。むしろ、それがスタートラインや。自分の弱さを受け入れて、初めて人は強くなれるし、他人に助けを求めることもできる。 - ホンマの「つながり」を大切にせなアカン
アーサーが最後まで求めた承認欲求は、一方的な熱狂や崇拝では満たされへんかった。ホンマの承認は、お互いを理解しようとする双方向の人間関係、つまり「つながり」の中からしか生まれへんのや。
『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、観る人を選ぶ「鏡」のような映画や。観ていて不快になったり、腹が立ったりするかもしれん。でも、その感情は、きっと自分自身の心の中にある何かを映し出しとるんや。
正直、この映画はエンタメとしてはめっちゃ不親切や。安易な答えをくれへんし、カタルシスもない。せやけど、これほどまでに「人間とは何か」「社会とは何か」「偶像とは何か」「消費するとはどういうことか」を考えさせてくれる映画は、そうそうないで。
一度と言わず、二度三度と考えてみる価値のある、とんでもない傑作(ただし“観客を選ぶ傑作”)。それが、ワイの結論や。
この映画を「駄作や!」って言う人も正しい。
だってそれは「偶像をもっと楽しませてほしかった」って欲望やから。ワイも映画館で観た時はそう思った。もっとジョーカー感を出してくれ!ってな。
でも逆に言えば、そこで腹立つってことは、この映画の仕掛けにまんまと絡め取られてる証拠やと思うんよな。
まとめ
- アーサーは「ジョーカーという偶像」に食われた男
- リーは「理解者」やなく「観客のメタファー」
- 群衆=ワイら観客自身
- ミュージカルは妄想であり、魂の叫びでもある
- ラストは両義的。でも大事なんは「偶像に殺された構造」
- この映画はSNS時代の偶像消費を描いた自己批評や
観終わったあとに胸がザワザワするのは、「ワイらもまた群衆やった」と気づくからやろうな。
参考文献↓
- https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ
- https://realsound.jp/movie/2024/10/post-1817669.html#google_vignette
- https://hollywoodreporter.jp/movies/70242/
- https://community.discas.net/announcements/ji5e2kf93htfecdn
- https://dream.jp/douga/tips_d/article28166.html
- https://note.com/sydligwillow23/n/n1c9dbdc65fe0
- https://note.com/tunacan/n/nc83a651e1be2
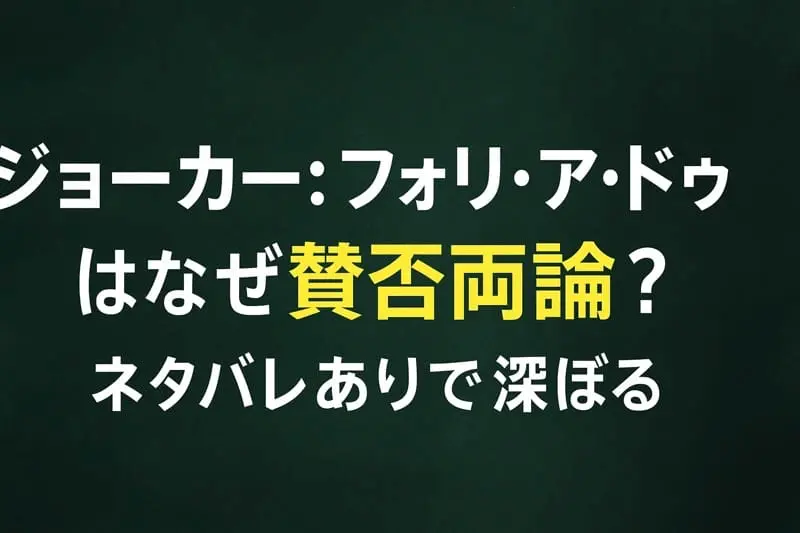
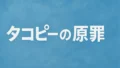
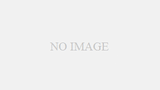
コメント