「めっちゃ面白い」という噂を聞きつけたので、『ザリガニの鳴くところ』を読んでみた。著者はもともと小説家ではなくて動物行動学の博士号を取得している科学者である。しかも普通の科学者ではなく、研究論文は科学者なら誰もが夢見るであろうネイチャーに掲載された実績のある、超一流の科学者なのだ。そんな聡明な科学者が、初の小説となる本を書き上げた。なんと書き上げたときの年齢は69歳だというのだから驚きである。
科学者が書いた本なのだから堅苦しいのかと思いきや、そんなことはなく、すらすらと頭に入ってくる(翻訳も素晴らしいのだ)。生物の専門家である著者が積み上げてきた動物の知識が随所に散りばめられており、それがこの本の深みを増し、圧倒的な描写になっている。夜の9時から読み始めて、夜中の2時まで一気に読んでしまった。
あらすじ↓
ノースカロライナ州の湿地で男の死体が発見された。人々は「湿地の少女」に疑いの目を向ける。6歳で家族に見捨てられたときから、カイアはたったひとりで生きなければならなかった。読み書きを教えてくれた少年テイトに恋心を抱くが、彼は大学進学のため彼女を置いて去ってゆく。以来、村の人々に「湿地の少女」と呼ばれ蔑まれながらも、彼女は生き物が自然のままに生きる「ザリガニの鳴くところ」へと思いをはせて静かに暮らしていた。しかしあるとき、村の裕福な青年チェイスが彼女に近づく……みずみずしい自然に抱かれた少女の人生が不審死事件と交錯するとき、物語は予想を超える結末へ──。
物語の舞台は、1950〜60年代のアメリカのノースカロライナ州の湿地帯。湿地になじみがないぼくたち日本人からすると「どんよりした沼」をイメージしそうだが、それは違うようだ。湿地は生命に溢れている。
湿地は、沼地とは違う。湿地には光が溢れ、水が草を育み、水蒸気が空に立ち昇っていく。緩やかに流れる川は曲がりくねって進み、その水面に陽光の輝きを乗せて海へと至る。p7
Googleの画像検索で調べると、湿地はこのようなイメージだ↓
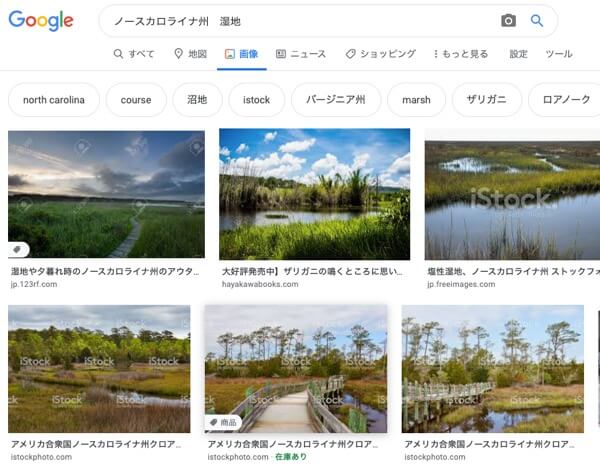
https://www.google.com/search?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E5%B7%9E%E3%80%80%E6%B9%BF%E5%9C%B0&safe=active&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk036nGxe9_N-bD0aoJc6lQx1mWJFqw:1592466874918&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5Wz8YrqAhXDfd4KHVSZBTEQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1876&bih=969
主人公のカイアは家族に捨てられた。その時はまだ6歳だった。酒に酔いたびたび暴力をふるうジェイク(夫)に身の危険を感じたマリア(妻)は、家を出て行った。計画的に出て行ったというよりは、精神錯乱状態になり、愛する子供達を放っておいて出て行かざるを得なかったのだ。母という家族をつなぎとめる存在を失ったカイアの兄弟たちも次々に家を飛び出し、最年少のカイヤだけが家に取り残された。
6歳のカイアはしばらくは父親と過ごしていた。ジェイク(父親)は戦争で負傷していたため国から障害者年金が出ていた。その中からわずかなお金をカイヤに渡し、自分は家に帰らないことも多かった。予想以上のネグレクトっぷりだ。そんな生活が3年ほど続いたが、父親もしばらくして失踪する。カイヤは文字通り、1人で生きていくしかなくなった。ちなみにカイヤは学校は1日で行かなくなり、社会福祉課からも逃げ続けている。(父親から、社会福祉課に見つかると里親に飛ばされ、里親はひどい奴ばかりだという洗脳を受けていたため。)
孤独な少女は貝や魚をとり、それを売って生活をしていく。湿地帯は生命が豊かなため、食べるのには困らないそうな。食べるものに困らなくても家族はいない、友達もいない。カイアの人生ハードモード感が辛すぎる。(この設定に「ちょっと無理があるんじゃね?」という疑問を抱きつつも、読み進めていく)
そんなカイアに転機が訪れる。カイアの兄の友達のテイトと接点を持てたことだ。テイトは交通事故で亡くした妹の面影とカイアを重ねたのか、カイアに熱心に勉強を教えてあげるようになる。カイアは学校に行っていないため、それまで文字も読めなかったのだ。ここからカイアの才能が爆発していく。文字を読めるようになったカイアは、テイトが渡してくれる本を次々と読んでいく。カイアが18歳になる頃には、そのへんの高校卒業者よりはるかに賢くなっていた。
テイトとの勉強の中でカイアは生物学に興味を持った。生命豊かな湿地帯に住むから当然といえば当然だろう。だけれど生物学に興味を持つもう1つ大きな理由は、「なぜ母親は自分の前から去ったのか?」という謎を解こうとしていたのだ。基本的に動物のメスは、我が子を大切にする。子を守るために命をかけて戦う。産まれた子どもの栄養源となるため、自分の体を差し出す昆虫もいるくらいだ。「子供のため」というのは、生物のDNAに刻まれているのである。「それなのになぜ母親は…?」、カイアはその答えを知りたかったのだ。父親の暴力に耐えきれなくなって家を出て行ったのは分かる、でもそれならなぜ迎えにきてくれないのか?なぜ手紙の1つでもよこしてくれないのか?母親の行動を知りたくて、カイアは生物学の本を読み続けているのだ(と思う)。
母親の気持ちを理解する一助となったのが、悲しいことに母親と同様、男からの暴力だった。その男は、本書の冒頭で死体で発見されたチェイスで、カイアの元彼だ。チェイスは酒に酔い、カイアに暴力をふるった。なんとか逃げ切ったカイアであったが、家に帰ればチェイスが待ち伏せしているかもしれないという恐怖に襲われる。そのときに、母親が家を飛び出した理由に気がついた。
母さんと同じで、自分の家に戻るのが恐ろしくてたまらなかった。その瞬間、にわかに霧が晴れたように、カイアはすべてを理解した。母さんがどんな目に遭い、なぜ去ったのか。p377
動物は時として、自分の身を守るために我が子を見捨てる。そこにあるのは『確率』だ。逃げた方が後々に遺伝子を残せる確率が高ければ、逃げる。では、人間はどうだろうか。この小説は、『動物』という観点から人の内面をえぐってくる。著者は、動物行動学の科学者として「人間という動物とは?」を見つめ続けてきただと思う。動物は繁殖することを第一に行動している。いわば遺伝子を次に残すためのマシーンだ。人間も同じなのではないか。人間も繁殖のためだけに生きていないのだろうか?「愛」というものは存在するのだろうか。
本書の終わりにはこのような言葉が書かれている↓
テイトの献身的な愛情のおかげで、人間の愛には、湿地の生物が繰り広げる奇怪な交尾競争以上の何かがあると気づかされた。けれどカイアは人生を通し、人間のねじれて曲がったDNAの中には、生存を求める原始的な遺伝子がいまなお望ましくない形で残されていることを知った。p498
動物を研究し続けた研究者の言葉である分、重みがある。ぼくたちの細胞1つ1つには、太古より刻まれているDNAがいまなお残っている。そのDNAたちがぼくたちの行動に作用しているのだ。ぼくはカイアと同様に、『交尾競走以上のなにか』を探し続けているのだと思う。
読書メモとして簡単に動画にしています↓↓↓
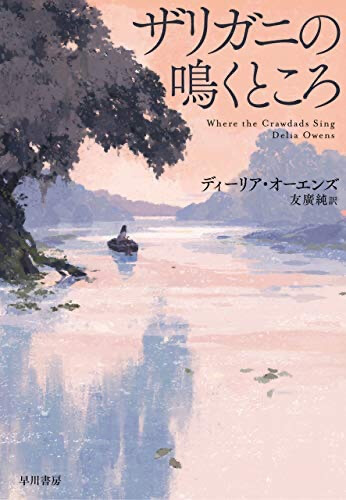


コメント